爬虫類飼育をする上で、毎日確認したいのがケージの中の温度です。
爬虫類は変温動物のため、体温は飼育環境の温度変化に影響を受けます。ケージの中の温度や湿度をこまめに確認することは、爬虫類の健康維持にとっても大切なことであると考えられます。
ヘビの飼育情報を収集していたとき、何名かの方がSwitchBotを使っているという情報を目にしました。
SwitchBotを使えば、ケージ内の温度や湿度を簡易的にスマホで確認できる…ということで、実際に我が家でも導入してみて、その便利さに驚かされました。
SwitchBotはすでにヘビを飼育している方や、ヘビの飼育をこれから始めたいという方にもぜひおすすめ。
ケージ内の温度や湿度を簡易的にスマホで確認したい!」という飼育者の望みを叶えてくれるのがSwitch botの温湿度計です。
■ 別室で作業していて手が離せないけどケージの状態が気になる。
■ 外出時に直接温湿度計の数値を確認できない不安を解消したいという方におすすめしたいです。
SwitchBotを導入するまでの経緯
ヘビを飼育する上で絶対に必要なのが温湿度計です。
アナログやデジタル表記などさまざまなタイプの温湿度計が発売されているので、ヘビ飼育者は使い勝手の良い製品を選んでいくつか購入することになります。
我が家のケージの中で使用しているものはすべてデジタル式の温湿度計です。
デジタル式の温湿度計は便利です。数字で表示されるのでひと目で温度と湿度がわかります。
しかし、これらの表示を確認するためには、実際に飼育部屋に行き、ケージを覗き込まなければいけません
忙しい時や外出時などは、どうしても直接ケージの中の温湿度計を覗き込むのは難しくなります。
ヘビを飼育するにあたって、外出先や飼育部屋から離れていてもケージの中の温度を確認できればなぁ…と思っていました。
SwitchBotとは
家電のスマート化を目的としたIoTデバイスです。SwitchBotによってスマート化した家電は、インターネット経由で遠隔操作することができます。
家電や照明のスイッチのオン・オフを切り替えたり、温湿度計が感知した温度条件と組み合わせて冷暖房の自動切り替えを行うなど、様々な事ができます。
SwitchBotを導入すると使える便利な機能一覧
温度・湿度をSwitchBot関連製品でモニタリングすると…
- 自室や外出先にいても、スマホのSwitchBotアプリを開けばケージの温度や湿度がわかる
- 生体を動物病院へ連れて行くとき、温度管理のために生体が入った入れ物を何度も覗き込まなくても良くなる
- 異常な温度上昇や低下を検知する設定をしておけば、異常を検知した際にスマホに通知してくれる
このように、爬虫類飼育者にとってたくさんのメリットがあります。
SwitchBot活用における注意点
様々な活用ができるSwitchBotの温湿度計ですが、インターネットへ常時接続していないと外出先からでは温度と湿度のモニタリングができないというデメリットがあります。
さらに、SwitchBot側の障害などで数時間にわたってスマホ⇔デバイス間での通信が不安定となり、リアルタイムでケージ内の状況を把握できないということも起こりえます。このため、ケージ内の温度管理をSwitchBotだけに任せるのは危険です。ケージの保温器具の調温はサーモで行い、SwitchBot関連製品は温度管理の補助として活用するのがいいと思います。
SwitchBot活用方具体例
ケージに取り付けた保温器具とサーモで温度管理+ケージ内にSwitchBotの温湿度計を設置することにより、温度や湿度の上下を時間、日、週、月ごとなど細かくモニタリングすることができます。
SwitchBotによる温度管理に必要なもの
- SwitchBotハブミニ
- SwitchBot温湿度計
温湿度計だけでは外出した時に温度湿度のモニタリングができないので、基本的にはインターネットに接続したハブミニを経由して、温湿度計が計測した数値をSwitchBotアプリに表示させる…という方法を取ります。
(外出先などから温度確認をしない、温湿度計をBluetooth通信のみで使用したい場合はハブミニは必要ありません)
インターネットに接続しているハブミニが温湿度計と通信し、スマホのSwitchBotアプリの起動に応じて最新の温度と湿度を表示してくれます。
SwitchBotハブミニの設定法について
SwitchBot温湿度計の活用方法について

SwitchBott温湿度計の裏側はマグネットになっているので、ケージ内の適当な場所に付属の金属プレートを取り付け、温湿度計を設置することができます。
温湿度計の場所がコロコロ変わると観測結果に影響がでてしまうので、なるべく同じ場所に設置したままの方が良いと思います。我が家ではケージの真ん中あたりの壁面に設置し、動かないように金属プレートと磁石で固定しています。
SwitchBot温湿度計の構造
温湿度計上部には溝があり、この中に湿度センサーがあります。
この湿度センサーが濡れてしまうと湿度表示に異常をきたすので、日々の水交換の際には温湿度計(の特に上部)を濡らさないように十分注意してください。
一度不注意で水滴を飛ばしてセンサーを濡らしてしまい、数時間ほど正確な湿度の計測ができなくなったことがあります。
上部についた水滴をティッシュペーパーで拭き取りドライヤーで大雑把に乾かした後数時間自然乾燥させると、また湿度計測が可能になりました。
素早く対処したことで湿度計足の機能を取り戻すことができたのかもしれないですが、たまたま計測機能が壊れず運が良かっただけということも考えられるので、できる限り濡らさないように取り扱うほうが良いでしょう。(今後計測値に異常が出ないとも限らないので)
SwitchBot温湿度計を導入してわかったこと、改善したこと
SwitchBott温湿度計をケージ内に設置して一週間程度の間に、いろんなことがわかりました。今までデジタル温湿度計で環境管理できていると思っていたのですが、自分が想定していた以上にケージ内の温度や湿度には波がありました。これをきっかけに飼育環境や気密性、飼育温度を見直すことができたので、SwitchBot関連製品を導入してよかったなと思っています。
①毎朝の冷え込みが思った以上にあることを数値として認識できるようになった
SwitchBot温湿度計を導入後、温度を頻繁に確認することができるようになったので、自分の寒さ対策の甘い部分を修正することができました。
SwitchBot温湿度計で計測された数値は、わかりやすいグラフで表示されます。このデータを元に、特に冷え込む時間帯にはサーモ側の設定温度を上げるなどの寒さ対策が取りやすくなりました。
②湿度を維持するために足りない要素を洗い出すことができた
温度とともに湿度もグラフ表示されるので、湿度が今現在どれくらいなのか一目でわかります。
湿度のグラフと数値は、湿度維持に何がどれくらい役立っているのか判断する手がかりになります。このデータをもとにして、湿度維持が不十分なエリアに加湿したりなど、環境を少しずつ改善していきました。
今は冬なので、秋口よりも更にケージの機密性をアップさせたり、ケージを覆う断熱材を追加したりなど細かに調整して、適切な湿度の維持を目指しています。
まとめ
SwitchBotの導入をきっかけに、飼育環境の改善を一歩すすめることができました。また、温度や湿度の維持に関して今まで以上にしっかりと取り組もう!という気持ちにもつながったので、今では飼育になくてはならない道具の一つになっています。
ただ、前述のようにSwitchBot側での不具合が発生する可能性は0ではないので、あくまで飼育環境維持の補助として活用するのが良いと思います
補助ではありますが、あるとないとでは大違いです。
ケージ内の温度と湿度の維持に役立つものがあれば、また記事にしてみたいと思います。
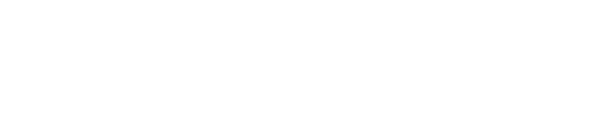


コメント