ヘビをお迎えする前に知っておくべき、動物病院とヘビの関係です。
動物病院の多くは、犬猫を対象とした診察を行っています。
爬虫類などエキゾチックアニマルと呼ばれる動物の診察ができる病院は数が少ないのが現実です。
ヘビが病気になったときのために、どこの病院につれていくか、どうやってつれていくか…などは事前に決めておくほうが良いと思います。
病気の対応は早ければ早いほどいいので、緊急時に大切な時間を無駄にしないためにも事前に確認しておきたいポイントをいくつかまとめてみました。
これからヘビをお迎えしたい!と思う方へ
①なぜヘビを診察してくれる動物病院が少ないのか?
②ヘビを動物病院で診察してもらえるかどうかの確認方法
③実際にヘビを動物病院に連れて行く手順
など、我が家での事例をもとにご紹介します。
①なぜヘビを診察してくれる動物病院が少ないのか?
世間一般的にはペットといえば犬猫です。他にも鳥類、ハムスター、フェレットなどが挙げられます。
そういった哺乳類・鳥類に比べて、ペットとして飼育されている爬虫類の数は少数です。
母体数が少ないため、必然的に爬虫類を診察してくれる病院も少なくなります。
爬虫類の中でもカメの診察が可能という病院は比較的見つけやすいですが、ヘビとなると更に数が絞られます。
・動物病院では犬猫の診察がメインなので、爬虫類を診察できる病院は少ない
・ヘビを診察できる病院となると更に少ない
これらのことは、飼育を開始する前に十分理解しておく必要があります。
自宅から移動できる範囲にヘビの診察が可能な動物病院があるか事前によく調べておけば、いざというときに焦らずにすむはずです。
②ヘビを動物病院で診察してもらえるかどうかの確認方法
動物病院のホームページで確認する、病院に電話して確認する等の方法があります。
我が家ではヘビをお迎えする前に、自分の住んでいる地域の動物病院のホームページを検索してヘビが診察可能かどうか調べました。
ホームページに爬虫類診察可と書かれていても、ヘビの診察が可能かどうかわからない…という場合、動物病院に電話で問い合わせしたりもしました。
グーグルマップやホームページを検索する他にも、ツイッターで爬虫類を診察可能な動物病院がまとめられていることもあるので、マメにチェックするようにしています。
ヘビの診察が可能な病院が見つかったら、診察日、病院までの距離、使用する交通手段と所要時間などについても合わせて確認します。完全な飼育初心者だったので、とにかく緊急時になって慌てないよう広く情報収集をしました。
③実際にヘビを動物病院に連れて行く手順
ヘビに異常が見られた場合、すぐに病院に連れて行く必要があります。②で確認した病院までの経路の情報を元に、すぐに準備を進めます。
ヘビをケージから出して移動させる際には十分に保温し、こまめに温度確認する必要があります。
我が家では以下ものを移動用として活用しています。
- 小さめのプラケース
- ペットシーツ
- アルミシート入り保温バッグ
- 使い捨てカイロ
- 温湿度計
プラケースにペットシーツを敷きヘビと温湿度計を入れ、それを保温バッグに入れて持ち運びます。
必要に応じて使い捨てカイロで保温し、こまめに温度確認も行います。夏場の車移動時には使い捨てカイロは必要ないことが多く、冷房をかけるくらいでした。
ヘビを病院に連れて行く場合、車での移動がおすすめです。車内の冷暖房を調節でき、人目を気にせず移動できるためです。
このほか、異常の内容・給餌量と頻度・ケージ内の温度と湿度・体重・排泄物の状態がわかるもの(写真や実物)・ケージの写真…など診察にあたって必要と思われる情報をメモなどして持っていきます。飼育に関しての指示内容を記録するため、ペンとメモ帳は持っていくと良いと思います。
日頃からヘビをよく観察し、気になることがあったら即病院へ!
爬虫類を診察できる病院が少ないという環境の中で、生体の健康を維持するためには、日頃の観察と異常を素早く発見することが大切だと思っています。
爬虫類はペットとしての歴史が浅く、病気や怪我等についてまだまだわからないことが多いのが現状です。
飼育の情報量に関しても、犬や猫などとはかなりの差があります。
そのため、基本的には病気になってからの対処ではなく、そもそも病気にさせない飼育が求められます。
ケージを清潔に保つ、ヘビが怪我をする可能性があるものをケージの中に入れない、過度なストレスを与えない、鮮度の良い餌を与えるなど、毎日のお世話を丁寧にしていくことを心がけるようにしています。
日々気をつけていたとしても、蛇が病気になるという事はあります。
そうした場合にはすぐに動物病院へ連れて行き、医師の診察を受けることが第一だと思います。
素人判断で異常を見て見ぬフリをするよりも、まず専門家の意見を仰ぐことが大切です。
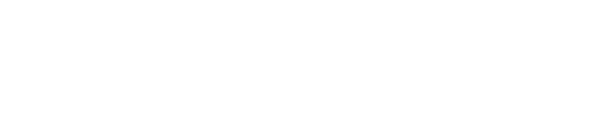

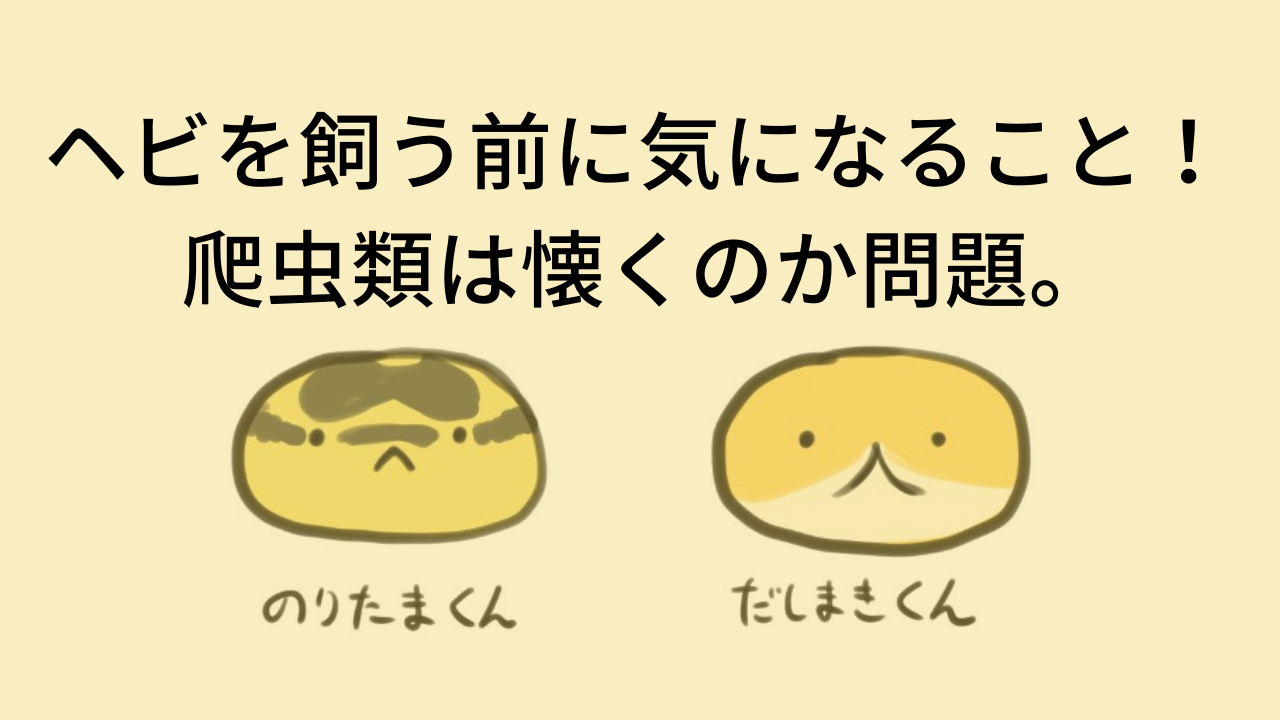
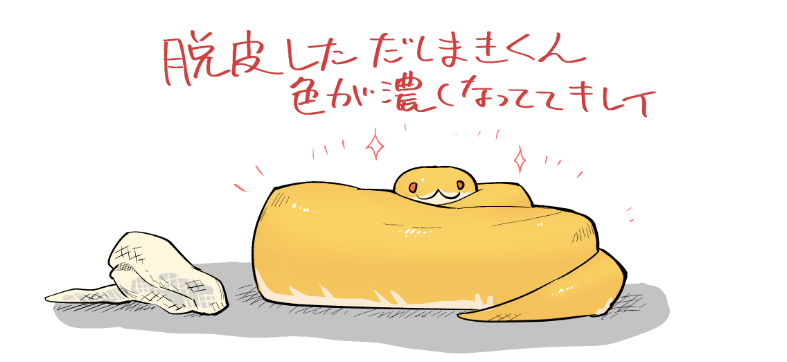
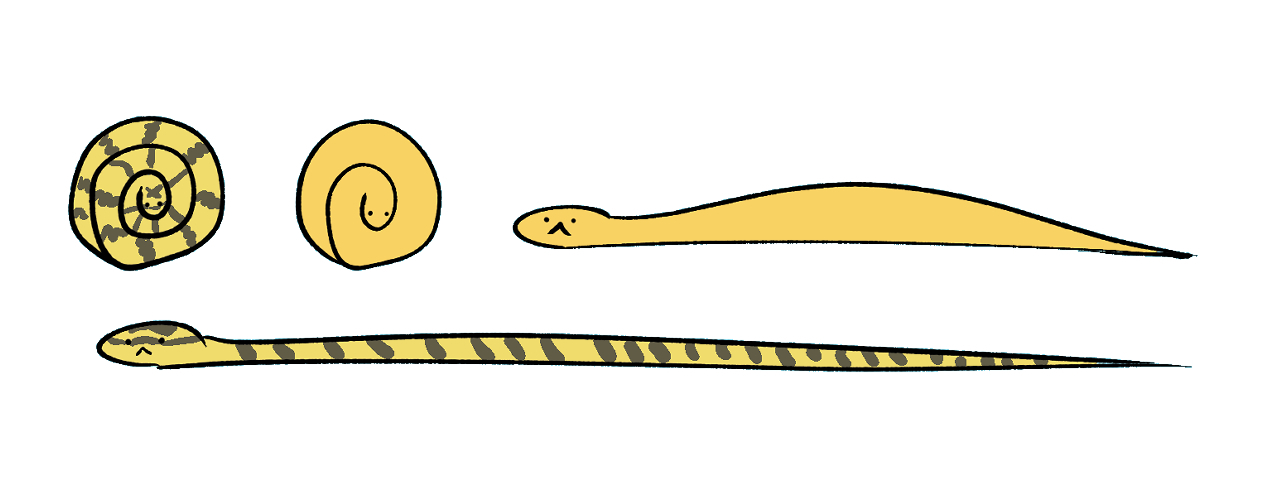
コメント